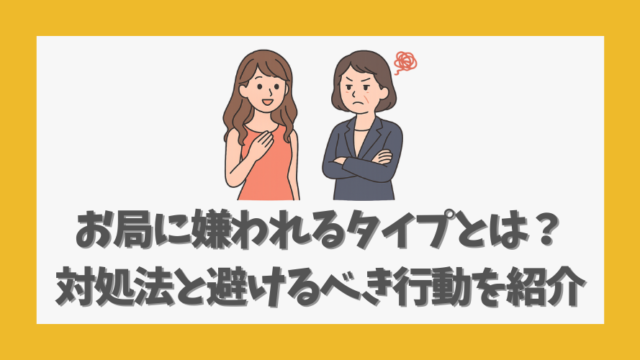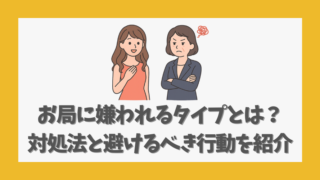「仕事が遅い人をずるい」と感じたことがある方は、決して少なくありません。自分は時間内に仕事を終わらせ、周囲に配慮して行動しているのに、手伝わない人や進行が遅い人の尻拭いまで求められると、しわ寄せを受ける側としては強いイライラを感じてしまいます。
とくに、真面目だけど責任感が強い人ほど、「また自分か」と感じる場面が多く、精神的にも体力的にも疲弊してしまいがちです。このような状況が続くと、「もう限界」「やめてほしい」といった思いが募り、仕事に対するモチベーションすら下がってしまうこともあります。
一方で、仕事が遅い人の性格には、完璧主義や優柔不断といった傾向が見られることがあり、中には病気や障害といった背景が潜んでいるケースもあるため、一概に「怠けている」と断じることはできません。
しかしながら、日々迷惑を被る側にとっては、そうした事情を知らされずにただ負担を背負わされるだけでは納得できません。
ときに、遅い人の影響で評価が下がったり、チームの士気が落ちたりすることすらあります。そして、迷惑をかけ続ける人がどのような末路を迎えるのかも、気になるところです。
この記事では、「仕事が遅い人をずるい」と感じる読者に向けて、感情との向き合い方、職場での適切な距離感、そして疲弊しないための対処法まで、多角的に掘り下げていきます。自分を守りつつ、健全な職場環境をつくるヒントとして活用していただければ幸いです。
この記事のポイントを紹介します!
- 仕事が遅い人がなぜ「ずるい」と感じられるのかの背景
- しわ寄せや尻拭いが特定の人に集中する理由
- 仕事が遅い人の性格や病気など見えにくい要因
- 迷惑を避けるための距離感や具体的な対処法
仕事が遅い人をずるいと感じる職場の現実
- しわ寄せが来るのはいつも自分
- 手伝わない人への不満がたまる理由
- 仕事が遅い人の尻拭いに疲弊する現場
- 仕事が遅い人の性格にありがちな傾向
- 真面目な人ほど損をしてしまう構造
しわ寄せが来るのはいつも自分
このような職場の悩みは、多くの人が一度は経験するものです。誰かの作業が遅れた結果、最終的に責任や追加のタスクが自分に降りかかってくる。こうした状況が続くと、業務へのモチベーションが低下し、精神的な負担も増してしまいます。
なぜこのような「しわ寄せ」が特定の人に集中するのでしょうか。
理由の一つは、仕事を早く正確にこなせる人に対して、「この人なら任せても大丈夫だろう」という評価が定着してしまうことにあります。いわば“頼られやすい人”が、意図せず負担を抱え込みやすくなるのです。
例えば、チーム内で期限が迫ったプロジェクトがあるとします。その中で誰かが作業を終えられなければ、進行に支障が出るため、最も信頼されている人が巻き取るしかありません。
結果として、もともとの自分のタスクに加えて他人の仕事まで引き受けることになり、業務量が倍増するのです。
こうした状況を改善するには、上司やチーム全体での「業務の見える化」が必要です。各メンバーの負荷を数値や進捗表で把握し、特定の人に負担が集中しないよう調整する取り組みが効果的です。
声を上げにくい場合は、週報や会議の場でさりげなく進捗を共有する工夫も有効です。
手伝わない人への不満がたまる理由
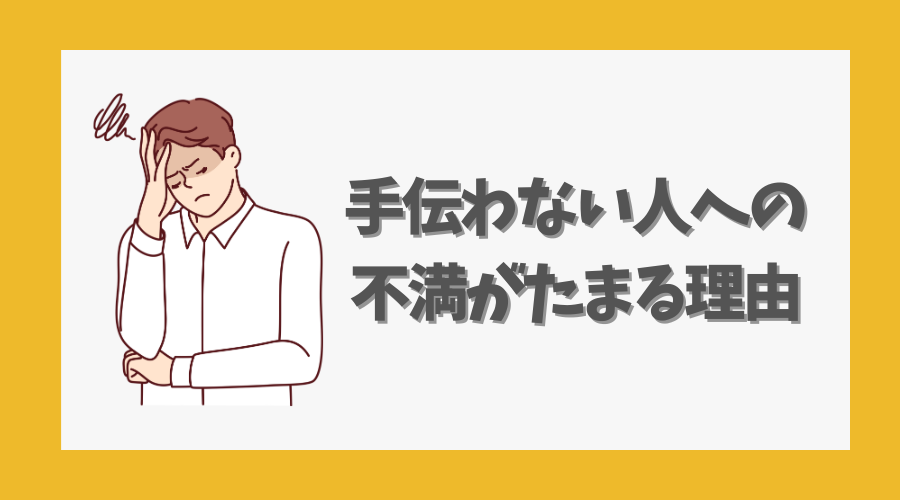
チームで協力して仕事を進める環境において、一部の人が「手伝わない」姿勢を取り続けると、自然と周囲の不満が蓄積していきます。この不満は、単なる作業量の不均衡だけでなく、「なぜ協力しないのか」という不透明さに起因するケースもあります。
一方で、手伝わない人にはそれなりの理由があることもあります。自分のタスクで手一杯だったり、他人の仕事に関わることでミスが発生するのを恐れていたりする場合です。
ただし、何も説明せずに「手伝わない」という行動を取ると、結果として「協調性がない」と受け取られがちです。
たとえば、チームで繁忙期に突入した際、他のメンバーが残業や対応に追われているにも関わらず、一人だけ定時で帰る人がいれば、周囲は「なぜ自分だけ楽をしているのか」と疑念を抱きやすくなります。
このような状況では、信頼関係が損なわれるリスクも高くなります。解決の鍵は「見える努力」と「明確なコミュニケーション」です。
手伝えない理由があるのであれば、その旨をきちんと伝えることで、無用な誤解を避けることができます。また、忙しい時期には小さなことでも積極的にサポートする姿勢を見せることで、チームの信頼を得やすくなります。
仕事が遅い人の尻拭いに疲弊する現場

仕事が遅い人がいることで、チーム全体の進行が滞り、結果として誰かが「尻拭い」をする羽目になる。
この構造は、特にスピードが求められる職場では深刻なストレス要因となります。尻拭いを担当する人が固定化してしまうと、その人にだけ負担が偏る事態にもつながります。
このような疲弊は、単なる業務負担の増加だけでなく、精神面にも影響を及ぼします。「自分がやらなければプロジェクトが止まる」「またあの人の分もやらされるのか」といった思考は、燃え尽き症候群や無気力感を引き起こす原因にもなります。
例えば、設計やチェック作業など時間のかかる工程で担当者の進捗が遅れてしまうと、その後の実装や納品作業を担う人にすべての遅れがのしかかってきます。スケジュール通りに動けないというだけで、周囲への負担が倍増するのです。
これを回避するには、「尻拭いを前提とした進行管理」を見直す必要があります。プロジェクトの初期段階で作業の割り振りや進捗の確認体制を整えておくことで、遅れを最小限に抑えられます。また、必要に応じて一部の業務を外注するなど、負荷分散の工夫も求められます。
チーム内で「誰かが助けて当然」という空気をなくすには、明確な責任分担と定期的な進捗確認が不可欠です。疲弊しない働き方を実現するには、個人の努力だけでなく、仕組み全体の見直しが求められるのです。
仕事が遅い人の性格にありがちな傾向
仕事のスピードには、スキルや経験だけでなく「性格的な特徴」も密接に関係しています。特に、仕事が遅いとされる人にはいくつか共通する傾向が見られることがあります。
まず挙げられるのが「完璧主義」の傾向です。細部までこだわりすぎるあまり、作業に時間がかかってしまう人は少なくありません。一つのタスクに何度も修正を加える、資料のフォーマットや表現に過剰に気を使う、といった行動がこれに該当します。
次に、「優柔不断な性格」も作業の遅さに影響します。判断を下すのに時間がかかる、選択肢があると迷って進めなくなるなど、決断のスピードが業務効率を下げる要因になります。このような人は、最終的に「誰かに確認しないと動けない」状態に陥ることもあります。
また、「自己主張が弱い」性格の人も、仕事が遅く見えることがあります。自信のなさから必要な確認をためらったり、問題があっても相談せずに一人で抱え込んでしまうため、業務全体の遅れにつながるケースもあるのです。
さらに、慎重でリスク回避を重視する性格の人は、「失敗しないように」と一つ一つの工程に多くの時間をかける傾向があります。このような姿勢は品質管理には役立つ一方で、スピードを求められる場面では不利に働きやすい側面も持ち合わせています。
このように、仕事が遅くなる背景には、怠けているわけではなく、性格的な特徴が深く関係していることも多いのです。職場では、こうした傾向を理解した上で、適材適所の業務配置やフォロー体制の整備が求められます。
真面目な人ほど損をしてしまう構造
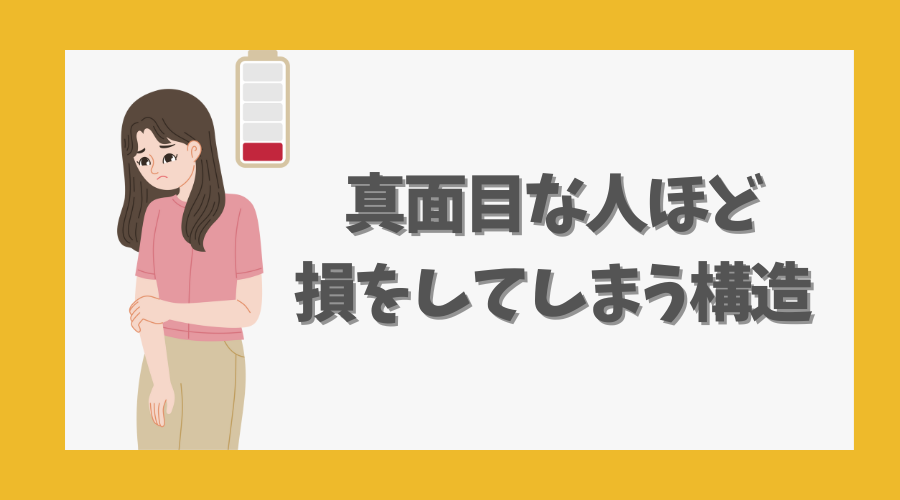
職場では「真面目な人」が高く評価される一方で、実際にはその真面目さが原因で「損をしてしまう」構造が存在します。責任感が強く、手を抜かずに業務に取り組む人ほど、負担が偏ってしまうことが少なくないのです。
まず、「頼られやすい」という特性があります。真面目な人は依頼を断らず、しっかりと対応することが多いため、結果的に他人の分まで引き受けてしまいがちです。
このような状況が繰り返されると、業務量が増えても周囲からは「当然」と見なされ、感謝もされにくくなるという悪循環に陥ります。
次に、「要領のよさ」を求められる場面で不利になることもあります。真面目な人はルールや手順を忠実に守ろうとするため、ショートカットや省略ができず、効率化の面で遅れをとることがあります。
結果として「仕事は丁寧だけど遅い」と見られ、不本意な評価を受けることもあるのです。
さらに、周囲のミスや遅れをカバーする役割を無意識に担ってしまうケースもあります。例えば、プロジェクトの進行が遅れているときに、自分の仕事を後回しにしてでも全体をまとめようとするなど、「他人のフォロー」が常態化してしまいます。
このような構造は、真面目さゆえの行動が評価されるどころか、むしろ損な役回りとして固定されてしまう危険性を含んでいます。こうした状況を防ぐには、自分の負荷を適切に伝えるスキルや、時には断る勇気も必要です。
また、組織全体としても、真面目な人にばかり負担が集中しないよう、業務のバランスを見直す仕組み作りが欠かせません。
仕事が遅い人をずるいと思った時の向き合い方
- イライラをためない工夫と考え方
- やめてほしいときに伝えるベストな方法
- 遅さの裏に病気が潜んでいることも
- 迷惑をかける側が迎える末路とは
- 自分を守るために意識したい距離感と対処法
- 仕事が遅い人をずるいと感じた時の現実と向き合うための総括
イライラをためない工夫と考え方
日々の業務で他人の仕事の遅さに直面すると、自然とイライラがたまってしまうことがあります。しかし、このストレスを抱え続けると、自分のパフォーマンスや人間関係にも悪影響を及ぼします。
そこで重要になるのが、「イライラを感じたときの対処法」と「ストレスをためない考え方」です。
まず、物理的な対処法としておすすめなのが、自分の業務に集中する時間を確保することです。他人の進捗に引きずられず、自分のタスクに集中できる時間帯を意識的に作ると、周囲の影響を受けにくくなります。
また、タスク管理ツールを活用することで、可視化されたスケジュールにより心理的な余裕が生まれます。
次に、心理的な工夫としては、「相手に期待しすぎない」姿勢が有効です。すべてを理想どおりに進めようとすると、思い通りにいかないことへの怒りや落胆が増してしまいます。
「人には得意・不得意がある」「すべてが自分の責任ではない」と捉えることで、ストレスの根本を緩和できます。
また、イライラを感じたらすぐに「深呼吸」や「小休憩」を入れると、感情のピークを抑える効果があります。無理に我慢するのではなく、こまめに気持ちを切り替える習慣を持つことで、冷静さを保ちやすくなります。
このように、自分の行動と考え方を少し変えるだけで、イライラの蓄積を防ぐことが可能になります。ストレスを感じやすい場面こそ、自分にとって快適な働き方を見直すチャンスだと考えてみてください。
やめてほしいときに伝えるベストな方法
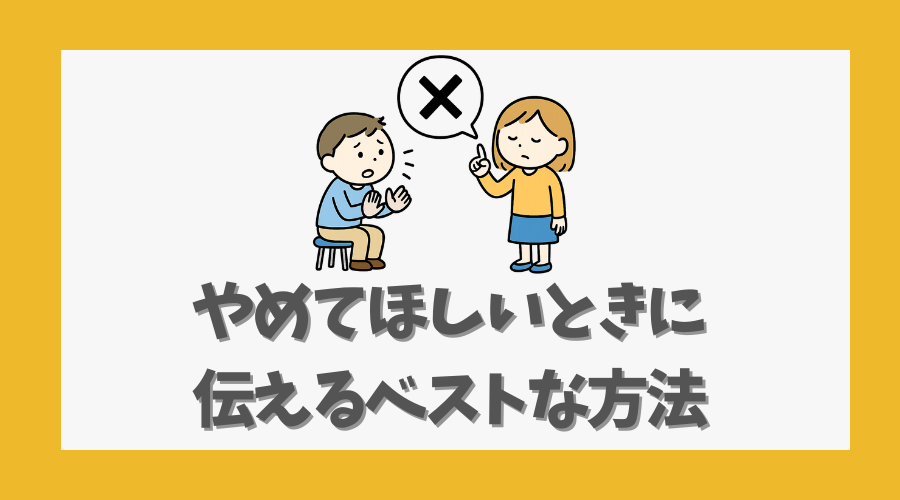
職場で他人の行動に「やめてほしい」と感じることがあっても、どう伝えるかは非常に繊細な問題です。伝え方を間違えると、人間関係が悪化したり、自分の印象が損なわれたりするリスクもあります。そのため、「タイミング・言葉選び・伝え方」の3つが重要になります。
まず大切なのは、感情的なときに伝えないことです。怒りや苛立ちをそのまま言葉にしてしまうと、相手に防御反応を起こさせてしまいます。冷静に状況を整理し、感情が落ち着いたタイミングで話すことが効果的です。
次に、言葉の選び方にも配慮が必要です。「やめてください」ではなく、「○○されると、少し困ってしまいます」「○○のほうが助かります」といった、相手を責めずに自分の立場から伝える表現を心がけましょう。
これにより、相手が自分を非難されていると感じにくくなります。また、伝える際は「1対1の落ち着いた場」で話すのがベストです。周囲に人がいると、相手が恥をかいたと感じたり、防衛的になったりしやすいため、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
さらに、伝えたあとに「フォローの一言」を添えることで関係性を保つことができます。たとえば「いつも助かっているので、今回だけちょっとお願いできたら…」など、日頃の感謝を言葉にすると相手も受け入れやすくなります。
このように、伝え方を工夫することで、不満を建設的な形に変え、職場での信頼関係を損なわずに改善を促すことが可能です。
遅さの裏に病気が潜んでいることも

仕事の遅さに対して「怠けているのでは」と感じることもあるかもしれませんが、実際には本人も気づかないうちに病気や障害が関係しているケースがあります。こうした背景を理解することは、過度な責任追及や誤解を防ぐために大切です。
一つの例として、「ADHD(注意欠如・多動症)」や「ASD(自閉スペクトラム症)」などの発達障害が挙げられます。これらの特性を持つ人は、スケジュール管理や優先順位の判断が苦手なことが多く、見た目には「仕事が遅い」「集中していない」と映ることがあります。
また、うつ病や不安障害などのメンタルヘルスの不調も、集中力や思考力の低下を引き起こし、業務のスピードに影響を与えることがあります。たとえば、単純な作業でもミスが増える、手順を忘れてしまう、やる気が出ないなどの兆候が見られることがあります。
厚生労働省の調査(令和2年度「労働者のメンタルヘルスに関する実態調査」)によると、職場でメンタル不調の兆候があると感じた社員が「対応できなかった」と答えたケースは30%を超えています。これは、周囲が「病気の可能性」に気づかず、適切な対応ができていない現状を示しています。
したがって、「単に仕事が遅い人」として片付けてしまう前に、その背景に病気や障害がある可能性も含めて考えることが重要です。本人の言動に違和感があったり、明らかに能力と結果が一致していないような場合には、産業医や上司と連携し、適切なサポート体制を整えることが求められます。理解と配慮のある環境が、結果的に全体の生産性を高めることにもつながります。
迷惑をかける側が迎える末路とは
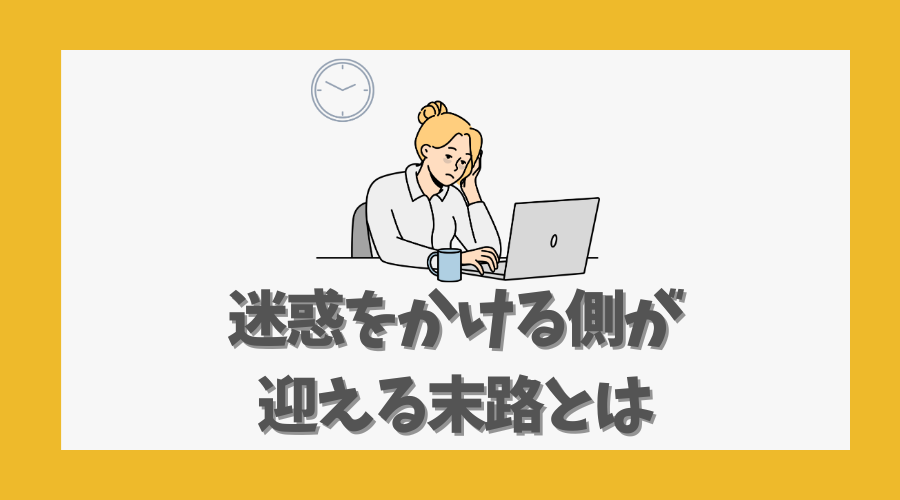
仕事が遅いことで周囲に迷惑をかけている人が、その状況を放置し続けると、さまざまな形で信頼を失っていきます。これは一時的な評価の低下にとどまらず、将来的なキャリアにも影響を及ぼす恐れがあります。
まず、最も顕著に表れるのが人間関係の悪化です。仕事の遅さは、直接的に同僚の負担増加や納期遅延につながるため、少しずつ不満や不信感が積もっていきます。
表面上は何も言われていなくても、陰で「あの人とは一緒に仕事をしたくない」と思われてしまう可能性が高まります。
また、評価・査定への影響も無視できません。たとえ誠実な姿勢で仕事をしていても、結果としてチームの進行を妨げていれば、上司や管理者の視点では「チーム貢献度が低い」と判断されてしまうことがあります。
その結果、昇進・昇格が遠のいたり、重要なプロジェクトから外されたりする可能性もあります。
さらに深刻なのは、職場で孤立してしまうリスクです。他者に頼られない状況が続けば、自信の喪失やモチベーションの低下を招き、悪循環に陥ることがあります。場合によっては、異動や退職の圧力を受けることすらあり得ます。
このように、迷惑をかけ続ける側は最終的に「信頼の剥落」「職場での孤立」「評価の低下」といった現実に直面することになります。
自覚がある場合には早期の行動改善が求められますし、自覚がない場合には周囲からのフィードバックをきちんと受け止める姿勢が重要です。
自分を守るために意識したい距離感と対処法

職場で仕事が遅い人と関わる際、過度に巻き込まれてしまうと自分の心身が疲弊してしまいます。こうした状況に陥らないためには、「適切な距離感」と「具体的な対処法」を持っておくことが欠かせません。
まず最初に意識したいのは、自分の業務と他人の業務を明確に分けることです。頼まれていないことまで進んで引き受けてしまうと、結果的に自分の仕事が圧迫され、ストレスがたまります。
「それは○○さんの業務なので、フォローが必要なら上司に相談してほしい」といった伝え方で、自分の境界線を守る姿勢が大切です。
また、「距離を取る」というのは単に物理的に離れることではなく、感情的に巻き込まれすぎないようにすることも含まれます。仕事が遅い人に対して苛立ちや焦りを感じたときには、深呼吸や一時的な作業の切り替えで、自分のペースを取り戻す工夫が有効です。
さらに、上司やチームリーダーとの連携も有効な対処法のひとつです。「○○さんの作業が滞っており、私の進行にも影響しています」と客観的に伝えることで、チーム全体のマネジメントとして対応してもらえる可能性が高まります。
これにより、自分一人で問題を抱え込まずに済むようになります。なお、表でまとめると以下のようなポイントが挙げられます。
| 状況 | 有効な対処法 |
|---|---|
| 頼まれていない作業が回ってくる | 担当範囲の明確化、やんわり断る |
| 感情的に疲れる | タイムアウト・短い休憩を入れる |
| 業務全体に支障が出ている | 上司へ状況を共有・改善策を相談する |
このように、距離を取ることは「冷たくする」ことではありません。自分を守りながら健全な職場環境を維持するための必要な対応と捉え、無理のない範囲で実践していくことが重要です。
仕事が遅い人をずるいと感じた時の現実と向き合うための総括
この記事のポイントをまとめていきます。
- 信頼される人ほどしわ寄せを受けやすい
- 作業が遅い人のカバーで自分の業務が圧迫される
- 協力しない人がいると職場の不満がたまりやすい
- 手伝わない理由が不明確だと信頼を損ないやすい
- 尻拭いが常態化すると疲弊と燃え尽きが起こる
- 進行管理が甘いと遅れの被害が特定の人に集中する
- 完璧主義や優柔不断な性格が仕事の遅さにつながる
- 真面目な人ほど損をする職場構造が存在する
- 頑張る人が報われず、無自覚な人が得をすることがある
- イライラを減らすには相手に期待しすぎないことが大切
- 「やめてほしい」は冷静に具体的に伝えるのが効果的
- 病気や障害が仕事の遅さに関係していることもある
- 遅れを続ける人は信頼やチャンスを失っていく
- 自分の限界を守るために境界線を意識する必要がある
- 問題は個人ではなく職場の仕組みで解決すべきである